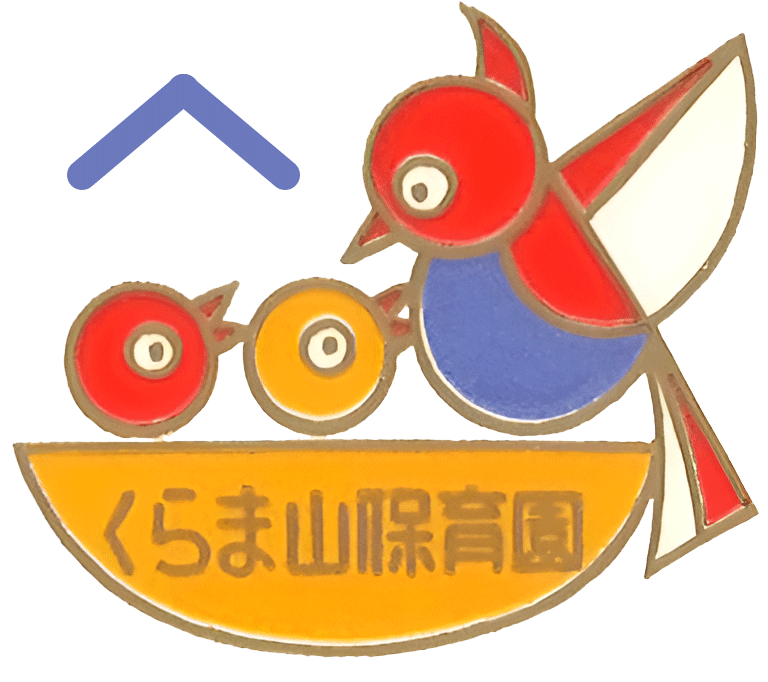日本赤ちゃん学会理事長の小西行郎先生のお話をうかがう機会がありました。小西先生は赤ちゃん学会「設立にあたってのメッセージ」(赤ちゃん学会ホームページに掲載)において、20世紀末の子どもをめぐる状況は、これまで私たちが持ってきた「子ども観」の見直しを我々に迫っているとの見地から、こんなことを述べておられます。
(以下引用)
一方、最近の神経科学の進歩は、「神経ダ-ウイニズム」という、脳は遺伝子で作られた粗い組織から無駄なものを削り取る2つの過程を経て成長するのではないかという概念を生み出し、また、発達心理や複雑系の研究では周囲からの刺激によって動くという原始反射は決して、新生児の行動の基本ではなく、新生児を自ら自発的に周囲に働きかける存在として捉えるべきではないかという研究が増えています。
こうしたいくつかの新しい考え方や所見は21世紀の「子ども観」を新たに構築するのに十分な可能性を持っていると考えられるのです。(引用ここまで)
近年顕著化している子どもをめぐる問題が、これまでの「子ども観」の結果だとしたら、それを早急に見直し、21世紀の新たな「子ども観」を構築しなければならず、そのためには子どもに関係する研究を行なうすべてのものが一同に介し、研究協力や討論を行なうべきだとおっしゃっています。
ここで「子どもに関する研究を行うすべてのものが一同に介し」とあるように、赤ちゃん学は、小児科学、発達認知心理学、発達神経学、脳科学、ロボット工学、物理学、教育学、霊長類学などの異分野研究の融合による新しい学問領域であり、21世紀最大の謎といわれる赤ちゃんの運動・認知・言語および社会性の発達とその障害メカニズムの解明から、ヒトの心の発達までを対象とする学問で、赤ちゃんを総合的に多面的な観点からとらえる、赤ちゃんを中心とした学問なのです。
様々な研究成果からわかる赤ちゃんの姿から、もう一度保育を考える必要があるかもしれません。