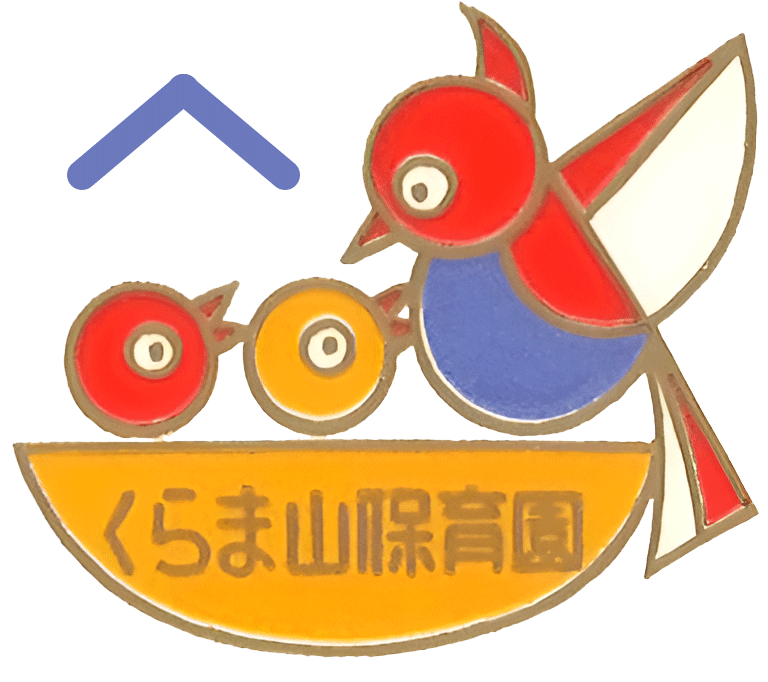チャレンジ体験に来ている洛北中学の2年生は、とても意欲的です。私が接しているのはお寺に体験に来ている10名ですが、何をするにも、さっと行動しますし、話しをすれば、しっかりと顔を見て聞いてくれます。みんなで声を出して般若心経を唱えましょうと促しました。たいていは後半にならないと声が出ないことが多いのですが、今年の子たちは初日から声を出していました。毎日午前中に行っている瞑想の時間も、30分間ほとんど動くことなく座っていますし、写経もとても丁寧にしています。
昼食は、音を立てないで食べる。食べ終わった後の食器をできるだけきれいにする。の2点に気をつけてほしいと伝えたら、器を置く音がしないよう工夫していましたし、食べ終わった後どうすれば器がきれいになるかいろいろ試していました。食器を片付けるのも、最初はそれぞれが自分の使った食器を持って返却場所に返しに行っていたのですが、2回目からは、先に食器を種類別に集めてそれを持って行く子、その間にテーブルを拭く子と役割を分担して片付けるようにしていました。
指導してくださったお寺の職員さんに聞いたら、掃除も丁寧にしていたようです。
自然の事象に触れて欲しいという願いから、毎年自然観察に関するメニューを入れていますが、今年はコウモリの観察をしました。担当してくださったのは、お寺で自然関係の調査研究をしていらっしゃる方です。お寺の建物にヒナコウモリというコウモリが集まって寒さをしのいでいる場所があります。今冬はとてもたくさんのコウモリが集まっていたので中学生にも見て欲しいという意図でした。ヒナコウモリが集団で越冬している場所というのはあまり見つかっていないようで、簡単に観察できるというのは全国でもめずらしいのだそうです。
でも、ただ見るだけではつまらないので、まず、コウモリの生態をすこし学んだ後、みんなでアクティビティーを楽しみました。コウモリが暗闇のなか超音波を使って獲物を捕まえたり障害物を避けて飛んでいるということをゲームにしたもので、目隠しをしたコウモリ役の人が、蛾の役の人を捕まえるというゲームです。とてもおもしろくて、みんな盛り上がりながら、コウモリの捕食行動を疑似体験していました。実際のコウモリを見たときもみんな興味津々で見入ったり、個体数を数えていました。
前向きに、積極的に行動する中学生達の姿が印象的だったチャレンジ体験でした。3日間があっという間に過ぎ去り、忙しいながらも、充実した楽しい時間を過ごすことができました。中学生の皆さんありがとうございました。